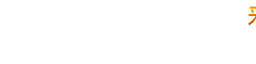�ɍ��킹���悤�ɂW���Q�U������P�O���Q�U���܂ň�ʎԗ���ʍs�~�߂ɂ��ēy���̉^����
�n�߂�悤�����C���̎����ɒʍs�~�߂ɂ��邱�Ƃ́C�}�C�^�P�̂���y���݂ɂ��Ă���
�����̐l�B�ɑ傫�ȃV���b�N��^���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�W���R�O���@�V�C�F����U���P�O�����ɉƂ��o���@�O�g�V���T���@�O�g��o���V���P�T��
�����͒N����ɍs�����Ղ͂Ȃ��������C�Q�`�R���O�ɂ͂��̎R�ɓ��������Ղ��������B
�}�C�^�P���V�`�P�O���ʑ�����������I�I�~���}�g���r�}�C�̖Ɍ���������������
�F�߂��Ȃ������B
�����̑�������������Ă݂����}�C�^�P�̔����͑S���F�߂��Ȃ������B
��ԉ��͓̌|�i�͂�̓|�j�ŗc�ۂQ��������ƌ��邱�Ƃ��ł����B
���������ꂾ��
����͖��肾���ѓ��̒ʍs�~�߂��ǂ�����čs���������悢���@���Ȃ����l���Ă݂����B

�R�͂܂��}�C�^�P�̋G�߂ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�E���o�~�\�E�i�~�Y�j�����J�S�i�t�̕t��������ł��Ń~�Y�̃R�u�Ƃ������j
���ł��������̂ł�����̎悵�Ă��܂����B
�������c����e���r���m��Βm��ق�����悳�����I
�X�^�Q�F���P�n�F�c���
���H���q��w����
�@�_�w���m�@�c���@���@�@�搶�ɂ���
�~�Y�̂��Ԃɂ��r�^�~���`�E�b�E�d��|���t�G�m�[�����Ïk����Ă����ڂ┧�̘V�����͂��߁C
�K����]�����E�S�؍[�ǂȂǂ�\�h����ق��~�Y�̃R�u�̃l�o�l�o�̓��`�����L�x��
�݂̔S����ی삵�ݒ��̓���������������Ƃ����Ă���B

9��5���@�V�C�F����T���P�T�����ɉƂ��o���喔��ѓ��ʍs�~�ߒn�_���U���O
�ʍs�~�ߗѓ����܂肽���ݎ��̎��]�Ԃ����O�g��܂Ō��������B
���͂R���̂Q�͉����čs�������A��͖��y�ł������B
���Ă���ѓ�������ċA�邱�Ƃ�������������B
�V���ɔ��������}�C�^�P�͂Ȃ������B�O����}�C�^�P�͑S�R�������Ă��Ȃ������B

9���P�P���@�V�C�F�_��T���P�O�����ɉƂ��o���@�ʍs�~�ߒn�_���U���@
��̑����O���猩��������I�I�~���}�g���r�}�C���Q���������Ă����B
�}�C�^�P�͌Â������ł���ƈꊔ�����������܂��Ⴉ�����B
���������ϲ


�}�C�^�P
9���P�Q���@�V�C�F�_��X�����ɉƂ��o���@
�V���J�V���W�̔�����c���̂��߂ɗY��������R���L�тɌ������B
���n�����V���J�V���W�P�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

���}�C�^�P
�V���t�͑�����������

9��17���@�V�C�F���� 5���P�O�����ɉƂ��o���@�O�g��6��10���@�O�g��o��6���P3��
�����͎�O�����邱�Ƃɂ����B
�O�g��㗬�Ɍ������ĉE���Ζʂ𗍂ށB
�L����Ɍ������č��Ζʂ̃}�C�^�P��������������Ă���Ƃ��C
�Q�{���т̐����̖ɐ��n�����}�C�^�P���o�Ă����B
�����̎��n��14kg


�O�g��ɉ����r���̎Ζʒ����ʼn����}�C�^�P�ɓ�����B


�O�g��P���Ԓn�_�̑����i���^�P���������Ă����B


�i���^�P�����n�_�̒����߂��̏����t�߂Ń}�C�^�P��ʂɍ̎悷��B
����܂ʼn�����̎悵�����Ƃ̂���ł��邪�C���N�͊m���x�Ǝv���B
����Ȃɑ������������̂����N�����߂ĂłR���łU�D�T�L���O�����������B



9��18���@�V�C�F����
4��45�����ɉƂ��o���@�O�g��5��55���@�O�g��o��6��
�����͎ʐ^���B��悤�ȃ}�C�^�P�ɏo���Ȃ������B
�Ⴂ�}�C�^�P�P�D�T�L���O���������Ȃ������B
�Q�������Ă̎R�����Ŕ�ꂽ�̂ŌߑO���ŎR�������B
9��20���@�V�C�F�܂� 4��30�����ɉƂ��o���@�ʍs�~�ߒn�_����5 ��20��
�������玩�]�Ԃɏ�芷����B
�O�g��5���S5��
�O����19���͈�����J�~�肾�����̂ō����͉J��̃}�C�^�P�ō̂�ł����B
![]() ���̃}�C�^�P�͂P�V���ɔ������m�F���Ă���R���ڂł������B
���̃}�C�^�P�͂P�V���ɔ������m�F���Ă���R���ڂł������B
���̖̓}�C�^�P�ʐ^�̑����B�e���L�m�R�ʐ^�ŏЉ�܂�����
�O��͕����P�Q�N�P�O���S���U���P�R���B�e�Œx����������Ǝv���Ă�����
���N�͂X���Q�O���ɔ������Ă����B
���������ă}�C�^�P�̔��������͋C�ۏ����Ȃǂ�
���łȂ����Ƃ��킩�����B
�Ⴂ�}�C�^�P



���̖͏��߂ĂŐ�����ꐡ�Ɖ߂��Ă����B
����̉J�ŔG��Ă͂������S�D�T�����������B
�傫���Ȃ����}�C�^�P

���̃}�C�^�P�͂R�N�O�ɂW�����{�ɔ��������ł��邪���̌�C���N�W�����{��
������Ă��邪�C�������N�͂łȂ��Ǝv���Ă������C�R��ڂł��̃}�C�^�P�ɏo�������B
�������������N�͋����Ă���B����͋ۂ̔���ɋC�ۏ����Ȃǂ�
�����ɉe�����Ă��邩�炾�Ǝv����B
���N�̗�Ă����̂��Ƃ������Ɍ������̂łȂ����Ǝv���B
����̃}�C�^�P

�����}�C�^�P�͑O�������Ƃ��͔����͑S���F�߂��Ȃ������B


���̎ʐ^�͍����̎��n����17.1kg


9��22���@�V�C�F�܂�S���R�O�����܂��^���ÂŃ��C�g�����ďo�����ʍs�~�ߒn�_����5 ��20��
�܂����Â��B
�������玩�]�Ԃɏ�芷��������5��30���C�O�g��ɒ�����6��
�����͎�O����O��c�����ӏ�����邱�Ƃɂ������C�w�ǂ���Ă����B
�c���Ă����̂��C�������ꊔ�ʼn��̎ʐ^�̒ʂ�B
�����̍��͎��s�������B����͎傽��ړI�n���Ō�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��B
���̖ړI�n�̂T���[�g���ʂ̏ꏊ�ɒn���̃L�m�R�̂薼�l�i�͕Ӓ��̓������̂V3�j��
�}�C�^�P���̎悵�č����Ă����B

9��26���@�V�C�F���J�`�܂�4��10�����܂��^���ÂŃ��C�g�����ĉƂ��o��B
�ʍs�~�ߒn�_����5 ���C�܂����Â��B
�S��50������k�C���암�̉Y�͒��ȂǂŐk�x6����ϑ�����n�k���������B
���x���̎��Ԃɗѓ��𑖂��Ă������ƂɂȂ邪�S�R������Ȃ������B
�h��͏H�c�����S��ɋy�Ƃ��邪�C�O�͐^���Âŗѓ����������đ����Ă��邩��ł��傤��
2��ڂ�6��8�����̒n�k���ѓ�������Ă������Ԃ������̎����C���t���Ȃ�������
���ꂾ���}�C�^�P�ɖ����ɂȂ��Ă��邩��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����͑O��i9��22���j�Ɏc�����ӏ�����邱�Ƃɂ������C�w�ǎc���Ă����B�܂��Ⴉ������
�y�j�`���j�Ƒ������Ƃ��l���č̎悵�Ă����B






�Ⴂ�u�i�n���^�P

���]�Ԃɏ���Ă̋A�蓹�C��������܂ʼn������Ă����Ƃ�
�X�M���w�тɃX�M�q���^�P���̂�ɂ��Ă����H�c�s���X�̂R�l�̏����̂P�l����Ăю~�߂��
�}�C�^�P�������Ă���Ƃ���ꂽ�B
���̐l���͓V�R�}�C�^�P���R�ɓ����č̂邱�Ƃ͓�����Ƃ��낤�Ǝv��
���������������ł͂Ȃ��R�l�ɂR���������܂����B
�ꐡ�����̎��n���ʂ́i�U�D�T�L���O�����j���Ȃ��Ȃ�����
��ϊ�ꂽ�̂ŗǂ��C���ł����B
10��1���@�V�C�F�܂�4��50���O����40���x�����܂����Â����C�g�����ĉƂ��o��B
�ʍs�~�߂͖�������������Ă����B�O��̋A��X���Q�U���ɒʍs�~�߂��������Ă�����
���̏�Ԃ��������ǂ����͔���Ȃ������B
�X���Q�U���̒��C���̒�����ɂ��Ă�����Ȏs�l�J�̕���
�͕Ӓ����ɍR�c�̓d�b�������ƌ����Ă����B
�}�C�^�P���̂��Đ��������Ă���l�����邱�Ƃ��������ꂽ�B
���̗l�Ȑl���̓d�b�Ȃǂɂ��R�c�ɉ͕Ӓ������ς���ꂸ�ʍs�~�߂�
����������Ȃ��������̂Ǝv����B
�����͒O�g��̑O��̑����̎Ζʏ㕔�������������Ζʂɂ킽�蒆�������f���ĉ�����B
�O�g���Ɍ������č����̊�Βn�̕t�߂̌͐ܖŃ}�C�^�P�P���C���̉��̐����łQ���̎悵���B
�A��͌��������̉��\�N�O�̔��o�H��������B
�i�O�g��̂����Ƃ��̔��o�H�łU�O�N�ȏ�o���Ă��邪�Ռ`���͂����肵�Ă���B�j
�����̃L�m�R�ʐ^�͉��̂Ƃ����B
�����̃}�C�^�P�̎��n�ʂ�2.5kg
�I�I�����C�^�P���R�{�̃~�Y�i����a�ɔ������Ă����B
�ʒu�I�ɂ͈�ԉ��n�ɂȂ�B
���̕t�߂Ɉ��ݕ��̋{�g�����̂Ă��l������C������F�Ǝv���邪�j��U�炩���Ă����B
�H�c���C�܂��͈��ݎc�����R�Ɏ̂Ă邱�Ƃ́C�R�������������łȂ��l�Ԃ��F�ɏP����
���������邱�ƂɂȂ���Ǝv���܂��B���������s�ׂ�J���Ă���܂��B
���͂ǂ�Ȃɏ����Ȃ��̂ł��R�ɂ͐�Ɏ̂ĂȂ��őS�������A��܂��B
�Ⴆ�ΌF�悯�Ƀ~�j�J�Z�b�g��K���g�т��܂��B�d�r�����Ղ���̂Ńf�W�^���J������p��
�j�b�P�����d�r���g�p���Ă��܂����C����ł�����P��͎��ւ��܂��B
���̓d�r�����������ȃZ���n���ł���ΎR�ɂ͎̂Ă܂���B
���ɂƂ��Ă͌F�悯�̃J�Z�b�g�e�[�v�͎R�����̕K���i�ł��B
�i�c�������Ȃ���̂��Ȃ���̎R�����͍ō��ł��B
�I�I�����C�^�P
���̃L�m�R�͓łł��B�v���I�ł͂Ȃ����C�ӂ邦�C���C�C�߂܂��Ȃǂ̏Ǐ�
�ł�Ƃ����Ă���܂��B

�܂����ʂɐH�ׂ�ƁC���o�C�������Ƃ��Ȃ����_�ُ̈틻���C������ԂɂȂ�Ƃ������Ă���܂��B
�R�`���іL�R�[�̑����ł͓Ŕ������ĐH�ׂ�Ƃ������Ă���܂����C�f�l�̐����@�͋֕��ł��B

�i���^�P

�O�g��̉��n������������Ζʂɂ킽�蒆�������f���ĉ�����r����
���}�u�V�^�P������
�É���w���_�����̐�����i�݂��̂������j���m���A�K���N�X����L�m�R�Ƃ��Ĕ��\�B

�́C�A�W�A�ɓG�Ȃ��ƌ���ꂽ�����̏��q����u�n�R�c�v�����p���Ċ����
�����͂ɂ��Ă����ƌ������L�m�R���������}�u�V�^�P
���������˓����i�z�E�g�E�N�E�j�Ƃ����B
�K���Ɍ����Ƃ����Ă����u���[�c�[�O���J���v�����łȂ�
�A���c�n�C�}�[�^�s���ǂŒ��ڂ���Ă���
�u�w���Z�m���v�Ƃ������������܂�ł���ƌ����Ă���B
�������}�u�V�^�P��
�{�P�Ɍ����E�K���Ɍ���
�����L�m�R�Ɛ��씎�m�͌����Ă���B
�����������}�u�V�^�P(�͔|)�͎s�̂���Ă���B
���܂ɂ́C���̃��}�u�V�^�P�i�͔|�j���X���ɕ��Ԃ��Ƃ�����B
�͐ܖ����}�C�^�P�P��

���̐����łQ���̎悵���B


10��7���@�V�C�F����6���߂��Ƃ��o��B
�O�g�������ɒ�����7�����y�����Ԉ��~�܂��Ă����B
�P�T���n�_���獶�̏�������Ζʂ�����B
���N�̎悵���ɍ�����Əo�Ă����B
���̏�̖i���N�̎悵���j�ɂ�����Əo�Ă��Ă������܂��̎�͂ł��Ȃ������B
���N�̃}�C�^�P�����ُ̈킳���͂����肵�Ă���B
���̎��ӂ���������S�R�Ȃ������B
��������܂�Ԃ��ĎΖʂ����f����B
�Ζʂ̕ψړ_�t�߂�3�{�Ƀ}�C�^�P���o�Ă������܂��Ⴉ�����B
���̃L�m�R�̎ʐ^�͂����̂Ƃ���B




�O�g����グ�ĎԂɖ߂����Ƃ��͂X���R�O����
��m��ɍŋߍs���Ă��Ȃ��̂ōs���Ă݂邱�Ƃɂ����B
��O��T���Ă݂����C�}�C�^�P�͑S�R�Ȃ�����������ƃN���^�P�ɓ������������B
�A�苦�a���̒m�荇���ƎԂ�u���Ă���Ƃ���ňꏏ�ɂȂ����B
���̂ЂƂ̓}�C�^�P���̂��Ă������C���͐��n��O�Ő��ۂ��������Ȉꊔ�����B
�Ⴂ�N���^�P

10��8���@�V�C�F����8���߂��Ƃ��o��B
�O�g�������ɒ�����9�����y�����Ԃ����������~�܂��Ă����B
�P���Ԓn�_���獡�N�܂������Ȃ����m�F���邽�߉���Ă݂����}�C�^�P�͑S��
���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
���N�ُ̈픭���ɂ��܂���Ă��̖�������o�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv��
�����ɉ�����ʂ������ƂɂȂ�B
�����߂��ȁ@�킳�т������@���L�^�P

����Ђ炽���ȁ@����Ђ炽�����@�`���q���^�P

10��11���@�V�C�F����6���߂��Ƃ��o��B
�O�g�������ɒ�����7�������y������2��~�܂��Ă����B
10��7���Ɏc���Ă����Q�{�̖�ړI�Ɍ����������O�̖͍̂��Ă����B
��̖͎c���Ă������܂��Ⴉ�����B
�C�����Ⴍ�Ȃ��Ă����̂Ő������x���Ȃ��Ă���B
���N�̃}�C�^�P�̂�͍������Ō�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
���̏o�����������R�i�O�x�C���x�j���B�e����B

10��21���@�V�C�F����8�������Ƃ��o��
�V�C���悢�̂Ŏʐ^���B��Ȃ���������R����������B
���L�^�P

�i���R���������J���ɂȂ��Ă���

�i���̖ɐ������u�i�n���^�P
�G�]�n���^�P�i�������k�P�I�`�E�k�L�E�`�j
�R�`���̒u���n���ł́C�������n���ďd����ŗ�����
�k�P�I�`���E���ɎR�ɍs���ƕ��������Ƃ�����B
����̓G�]�n���^�P�̔����ꂪ���̃L�m�R�̏{�Ȃ̂ł���B
���X�Ђ��͍ō��Ŕ鋫�̖����ƌ����l������B
��ϋM�d�ŃV�[�Y�����ɓ�����̂���ł���B

�i���^�P�ӏH�ɐ�����R�S�����^�V(������)�̗c��

�Z�J��/�〈��
2003/10/21/�B�e�v
10���R1���@�V�C�F����V�����߂��Ƃ��o��
�V�C���悢�̂ŎR�̍g�t���ʐ^�Ɏ��߂Ȃ���������R����������B
���N�Ō�̎R�����ɂȂ邩������Ȃ��B
�݂��Ȃ�̑�a�ɕt�������I�V���N�W�f���_
���a�S�S�N�W���Q�W���m�ʍ����̐X�ɓV�c�É��i���a�V�c�j�s�K�ɂȂ�
���̎U���H�̋߂����g�`�m�L���t������
�I�V���N�W�f���_�ɊS����ꂽ�ƕ����Ă���܂��B
�O�g��̑����͗��ɔ����������L�^�P

���������Ȃ����i���R
�O�g����������藎�t���č����R�͎��F�ɑ����Ă��܂����B
��n�ł͍g�t�^������
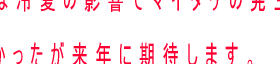
�Z�J��
���̉摜�Ƀ����N��}�����Ă��Ă��܂��B
�N���b�N����ƃg�b�v�y�[�W�ɖ߂�܂��B
11��14���@�V�C�F����9�����߂��Ƃ��o��
���N�̎R�����͏I���ɂ�������ł��������C�����͂��܂�V�C���悢�̂�
�܂��R�ɍs�������Ȃ��ĂX���߂��ɏo�������B
���̎R�����̓L�m�R�Ȃǂ��̂邱�Ƃ�茒�N��ۂ��Ƃ̕��ɕς���Ă����B
���N�̂��߂ɂ͕������Ƃ���Ȃ��Ƃ��������Ă��Ă�
�R�łȂ���Ε����C�ɂȂ�Ȃ��B
�ѓ��̓y���^�����P�Q����{�܂ʼn�������C�܂���^�g���b�N�̓y���^����
�ѓ����r��Ă���̂ʼn��n�ɍs�����Ƃ�f�O�����B
�������@�ܘY���̌�����������Ă݂邱�Ƃɂ����B
���̎ʐ^���T���N���~�Ɖ��w�A���������E�����V�_


�T���N���~���v���o�������Ƃ�����B
����S����ɏ��߂ċΖ������������̏㗬��
�������č��Ɏw�������������̖���ł����B
���������ʗp�ނ̎��n�����ɍs�������̂��Ƃł���B
�T���N���~�̎����͂R�O���[�g���ɋ߂����̂���ł����B�n���i�Y�����H�m�{������j�ł�
�T���N���~�����V�ƌĂ�ł������Ƃ��v���o�����B
���m����̓C���i�������ŁC�n���𗣂�Ă�����ނ�ɉ��s�������Ƃ����邪
�܂��������s���Ă݂�����ł͂��邪�C������Ɩ����ł��傤�B

�c���}�T�L�Ŏv���o�������Ƃ�����B
�v������̐R�c��ł���������c�̂Ȃ��Ō��X�A�̂j����
�X�M�̖ɂ���݂��u�c���v�����Q�������Ă���Ɣ������ꂽ�B
�c���}�T�L�Ǝv������g�v��ے����R�����g�������Ƃ��������̃T���N���~��
����݂��Ă����c�������Ďv���o���ꂽ�B
���͓����Ґ����ł͂Ȃ��������v��ۂ̈���Ƃ��ĕ����Ă�����
���̓X�M�̐��ɂ���݂��c�����c���A�W�T�C
�i�ʖ��F�S�g�E�d���C�c���f�}���j����ԑ����Ǝv���Ă���B
���̑��̃c���ނƂ��Ă���܂ł̎R�����③�ю��Ƃ����s���Ă����o������
�C���K���~�C�}�^�^�r�C�N�Y�C�t�W�C�c���E�����h�L�C�N���d���C���}�u�h�E�C�m�u�h�E�C
�T���J�N�d���C�c�^�E���V�C�T���i�V�i�R�N���j�C�~�c�o�A�P�r�C�c�^�C�c���}�T�L�D
�L�d�^�C�}�c�u�T�C�~���}�N�}���i�M�C�N�}���i�M�Ȃǂ��v���o�������C
�܂��Y��Ă�����̂����邩���m��Ȃ��B